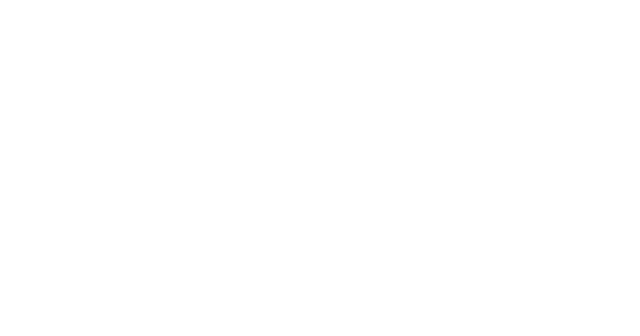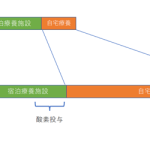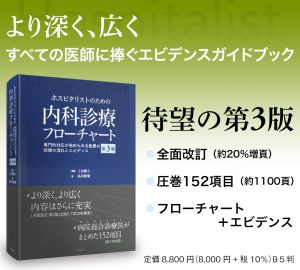成人の感染症の治療期間は
“shorter is better”
はじめに:感染症専門医を悩ませる質問とは
感染症診療の原則は患者背景と臓器、そして微生物であり、この3つが決まれば抗菌薬は決定できる。学会発表や症例検討会では、まれな症候群や微生物の感染症の診断が付いて治療が開始されるところで話が終わることが多いが、臨床では抗菌薬を開始するところがゴールではなく抗菌薬を開始したらいつかやめねばならない。「私にはスタートだったの、あなたにはゴールでも」と歌ったヒット曲が昔あったが、感染症の治療においても当てはまると言えよう。
米国の感染症科医で、ブログ”HIV and ID observation“を運営していることでも有名なPaul Sax医師も、感染症コンサルテーションで最も多い質問の一つが「抗菌薬の投与期間はいつまでか」であると記している[1]。米国では入院期間の短期化の圧力が強く、点滴抗菌薬終了とともに退院させるため、このような質問も多くなると推測される。筆者も日本の現場でのコンサルテーションの経験から、やはりこの質問は最も多く、なおかつ答えにくいものの一つであると感じている。抗菌薬適正使用の観点からも、抗菌薬の投与期間は治療がうまくいく範囲で最小限にとどめなければならない。
本稿では、最近になり臨床研究の光が当たり始めた抗菌薬の投与期間の考え方、そしていかにしてこれから投与期間を短縮していくかについて簡単に解説を試みる。なお、成人の感染症についての記載であることをご了承いただきたい。
投与期間決定へのアプローチ:診断を決めて推奨に従う
最初に紹介するアプローチは「診断が決まれば投与期間も決まる」である。「発熱(or CRP高値)で抗菌薬を開始したのですが、これはいつまで続ければよいでしょうか」という質問に対しては適切な回答を用意するのは困難である。というか、質問自体が間違っている。「間違った問いに対する正しい答えほど、危険とは言えないまでも役に立たないものはない」と経営学者のピーター・ドラッカーも述べている[2]。
抗菌薬の投与期間を決めるのは本来、抗菌薬を開始した医師であるべきである。診断を付けずに発熱や炎症反応高値に対して脊髄反射的に抗菌薬を開始したら、投与期間の正解を探るべくもない。診断というのはこの場合、感染症を起こしている臓器の臨床診断±微生物学的診断である。蜂窩織炎や市中肺炎では微生物学的診断に至らない例が大半を占めるが、少なくとも臓器の診断が付いていれば抗菌薬の投与期間を考える土俵に立つことはできる。感染症の臓器診断ごとに推奨される投与期間は、ある程度コンセンサスが得られているからである。例えば、筆者が修行時代からよく参照しているSanford感染症治療ガイドの表から、肺炎の部分を抜粋して引用すると表1のようになっている。
| 診断 | 治療期間 |
|---|---|
| S. pneumoniaeによる肺炎 | 最短5日、解熱後3-5日 |
| 市中肺炎 | 5日、解熱後2-3日 |
| 腸内細菌科またはPseudomonasによる肺炎 | 21日、しばしば最大で42日 |
| Staphylococcusによる肺炎 | 21-28日 |
| Legionella、Mycoplasma、Chlamydiaによる肺炎 | ドキシサイクリンまたはフルオロキノロン系薬では7-10日、アジスロマイシンなら5日と短い |
| 肺膿瘍 | 通常は28-42日 |
なお、冊子版のSanfordでは治療期間をまとめた表は全部で1ページ(日本語版では3ページ)に収められている。そのためか普段からSanfordを愛用している医師でも存在を知らないことがある。
さて、これが絶対的な基準かというと無論そんなことはなく、Johns Hopkins MedicineのAntibiotic Guideline 2015-2016(有名なABX Guideとは別。以前はインターネットで閲覧できたが現在はできなくなっている)の記載では次(表2)のようになっている。
表2 抗菌薬の投与期間の推奨例その2:Johns Hopkins| 診断 | 治療期間 |
|---|---|
| 市中肺炎 合併症のない健康成人 | 3-5日 |
| 市中肺炎 免疫不全/肺の解剖学的異常 | 7日 |
| 市中肺炎 治療抵抗性、初期治療の失敗 | 10-14日 |
| 医療関連肺炎 | 5-7日 |
Sanfordと比較すると状況の分類が異なり、推奨する治療期間にも違いがあることが分かる。臓器の診断が決まれば感染症の治療期間も決まるというのが原則だが、この治療期間の推奨というのも実は典拠によりばらつきが大きい。
治療期間はどうやって決まったのか
では、これらの投与期間はどのように確立されてきたのだろうか。抗菌薬治療の歴史をさかのぼると、ごく短期間の抗菌薬投与でもしばしば有効であるという事実が古くから知られていた。1943年の報告では、肺炎球菌肺炎に対してペニシリンの2-3日の投与で十分に患者が回復したとされている[3]。
しかし、抗菌薬の開発が進み、多くの医師にとって容易に処方できるようになる過程で、「臨床的に改善が得られてからも再燃を防ぐために数日間追加で投与する」というようなプラクティスが広まっていった。そうして抗菌薬の投与期間は少しずつ長くなり、経験的に確立されていったものと推測される[4]。米国感染症学会のガイドラインで推奨されている治療期間の多くが、現在の基準に照らせば良質なエビデンスに基づいて記載されているわけではないことも指摘され、科学的に検証した抗菌薬投与期間の設定が必要であると提唱されている[4]。
最近の治療期間短縮の動き
抗菌薬の最短投与期間についての研究は、近年まで積極的に行われていなかった。臨床医は短期間投与による治療失敗を恐れ、ほとんどの患者の感染症が再燃しない程度の治療期間を設定することにインセンティブが働くものである。抗菌薬の開発が華やかなりし頃であれば、抗菌薬を開発した製薬会社にも治療期間を短縮するインセンティブは生じなかった。しかし、近年になり新規抗菌薬の開発が滞り、耐性菌の拡大が問題になってきて、抗菌薬の投与期間についてもよりエビデンスを積み重ねて適正化するような動きが出てきた。このため市中発症の肺炎、尿路感染、軟部組織感染といったcommon diseaseである感染症に対する抗菌薬の投与期間の短縮が試みられ、研究結果が集積してきている[5]。
現時点でのまとまったものを表3に示す。なお、この表はSpellbergによる総説に記載されているものを元にしている[6]。Spellbergは今後の感染症の治療期間として“5 is new 7”というフレーズを提唱している。われわれは1週間の単位でものを考えることが多いため、つい治療期間も7日、14日……と考えがちであるが、このコンスタンティヌス大帝が定めたことにさかのぼるという1週間の区切りに縛られずに、より短い5日を単位として治療してはどうかという提案である。確かに、Spellbergによる表を見ると短期治療群では5日を基準とした研究が多い。
表3 短期治療群が長期治療群と遜色ないと報告されている感染症| 疾患 | 治療日数 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 短期群 | 対照群 | ||
| 急性細菌性副鼻腔炎 | 5 | 10 | 同等 |
| 腹腔内感染症 | 4 | 10 | 同等 |
| 市中肺炎 | 3-5 | 7-10 | 同等 |
| 骨髄炎 | 42 | 84 | 同等 |
| 院内肺炎 | ≦8 | 10-15 | 同等 |
| 腎盂腎炎 | 5-7 | 10-14 | 同等 |
| 軟部組織感染 | 5-6 | 10-14 | 同等 |
バイオマーカーを活用した個別化の試み
抗菌薬の投与期間の最適化において、理想となるのは個別化である。すなわち、患者個々の状態に応じて、感染症を治癒に導ける最短の期間をオーダーメイドで設定して治療できれば最善である。残念ながら、現在までに得られている知見をフルに用いても、オーダーメイドで治療期間を設定することは困難なことがほとんどである。「念のため」という理由で抗菌薬の投与を長期化させず、エビデンスのある範囲から積極的に短期治療へと切り替えていくことが、これからの感染症診療にまず求められていると言えるだろう。
より個別化した治療期間を設定するために、バイオマーカーを用いる方法も試みられている。昨今主に用いられているのはプロカルシトニン(PCT)である。例えば市中肺炎であれば、PCT<0.1μg/Lまたは80-90%以上低下という基準に従うことで抗菌薬の使用量を減らし、かつ治療のアウトカムも遜色なかったと報告されている[7]。他にも髄膜炎、敗血症などの重症感染症、気管支炎、閉塞性肺疾患の急性増悪などで活用が試みられている。バイオマーカーとしてのPCTは、これら個別の感染症における抗菌薬投与終了を判断する際の参考以外に、外来での上気道炎に対する抗菌薬投与の適否、集中治療室管理の敗血症患者における抗菌薬の終了といったシチュエーション別の症候群におけるアプローチでも用いられている[8]。PCTを診療に取り入れる際は目的をはっきりさせ、結果によって診療をどう変更するのかをあらかじめ決めた上で測定することが重要である。
治療期間短縮が困難な感染症
短期投与が不可能な感染症とはどのようなものであろうか。専門家によって意見が分かれるかもしれないが、筆者が挙げるのは表4に示す5つである。これらについては、まだ積極的な短期治療の試みは控えたほうがよいのではないかと考えられる。
表4 短期治療の試みが困難な感染症の例| ・S. aureus菌血症/感染性心内膜炎 ・その他の感染性心内膜炎 ・髄膜炎/中枢神経感染 ・壊死性軟部組織感染症 ・膿瘍性疾患(ドレナージがされない場合) |
重症またはクリティカルな臓器における感染症では、しばしば抗菌薬の長期投与を余儀なくされる。これらの臓器の感染症の場合は、現行のガイドラインの記載に則った治療期間を完遂するのが現時点では慎重なやり方と考えられる。これらの感染症についても治療期間の短縮の研究は行われており、最近も心内膜炎に対する治療レジメンを部分的に内服抗菌薬にしても全期間を点滴で行う場合と比較して遜色なかったとする報告がある[9]。とはいえ、これらの研究ではすでに安定した状態になった患者を対象とするなど患者背景や重症度が限定されていることもあり、自分の眼の前の患者に当てはめられるかどうかはよく吟味する必要がある。膿瘍性疾患は、抗菌薬の投与期間の設定が難しい感染症の最たるものである。専門家によって多少スタンスは異なるが、基本は「治るまで」である。「治る」の定義が難しいところだが、筆者は「画像で消えるか、固定するまで」を採用することが多い。S. aureus菌血症においては血液培養陰性から14日あるいは28日以上の適切な抗菌薬の投与が必須とされるのは、S. aureusという細菌の「一度血流感染症を起こすと血管内感染、心内膜炎、膿瘍形成など合併症が非常に多い」という特異的な性質が理由となっている。
治療期間を短縮するのは感染症専門医にとっても難しいことが多い。海外からも感染症科医はしばしば長めの治療期間を推奨しがちであると報告されている[10]。現在、筆者の勤務先でも抗菌薬適正使用ラウンドのために抗菌薬の1週間以上の投与例を長期投与例としてピックアップしているが、しばしば感染症科が介入中の症例が一覧の大半を占めてしまい居心地の悪い思いをする。一つ言いわけをさせていただくと、難しいケースだからこそコンサルテーションが必要なのであり、長期投与が必要な症例だからこそ感染症科医が介入しているのであって、情状酌量の余地はあると申し上げたいところである。
まとめ
抗菌薬の治療期間の考え方について述べてきた。治療期間の設定は、治療している病態を適切に把握した上で行う精密な行為である。重症で複雑な病態ほど治療期間の設定が難しいことは強調しておきたいが、common diseaseとして遭遇する軽症~中等症の感染症については耐性菌の選択圧を下げ、副作用を減らすという抗菌薬の適正使用の一貫として、適切に病態を把握した上で治療期間の短縮に積極的に取り組んでいただければ幸いである。これからの抗菌薬投与期間は“shorter is better”である。
【References】
1)How to Figure Out the Length of Antibiotic Therapy [Internet]. HIV and ID Observations. 2010 [cited 2018 Nov 19].https://blogs.jwatch.org/hiv-id-observations/index.php/how-to-figure-out-the-length-of-antibiotic-therapy/2010/10/22/
2)P.F.ドラッカー: ドラッカー名著集3 現代の経営[下], ダイヤモンド社, 2006.
3)Keefer CS, Blake FG, Marshall EK, et al: Penicillin in the treatment ofinfections: a report of 500 cases. JAMA. 1943 Aug 28; 122(18): 1217-24.
4)Rice LB: The Maxwell Finland Lecture: for the duration-rational antibiotic administration in an era of antimicrobial resistance and clostridium difficile. Clin Infect Dis. 2008 Feb 15; 46(4): 491-6.
5)Royer S, DeMerle KM, Dickson RP, et al: Shorter Versus Longer Courses of Antibiotics for Infection in Hospitalized Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Hosp Med. 2018 May 1; 13(5): 336-42.
6)Spellberg B: The Maturing Antibiotic Mantra: “Shorter Is Still Better”. J Hosp Med. 2018 May 1; 13(5): 361.362.
7)Schuetz P, Müller B, Christ-Crain M, et al: Procalcitonin to initiate or discontinue antibiotics in acute respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12; (9): CD007498.
8)Sager R, Kutz A, Mueller B, et al: Procalcitonin-guided diagnosis and antibiotic stewardship revisited. BMC Med. 2017 Jan 24; 15(1): 15.
9)Iversen K, Ihlemann N, Gill SU, et al: Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis. N Engl J Med. 2019 Jan 31; 380(5): 415-24.
10)Macheda G, Dyar OJ, Luc A, et al: Are infection specialists recommending short antibiotic treatment durations? An ESCMID international cross-sectional survey. J Antimicrob Chemother. 2018 Apr 1; 73(4): 1084-90.