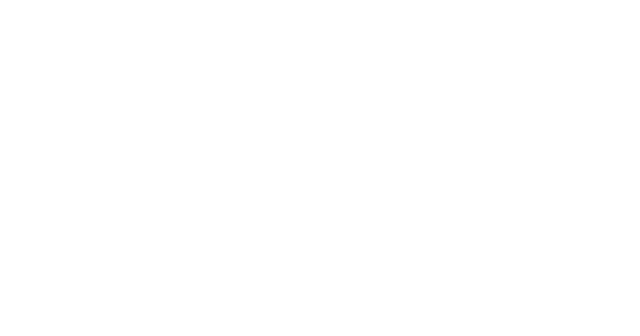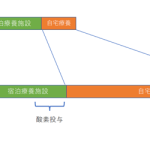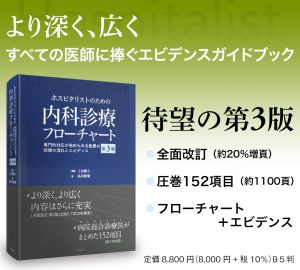繰り返す発熱と自己炎症症候群――感染症科医のためのprimer(2/4)
(今号は4週連続で配信しています。 1回目)
研修医しまむら(以下「しまむら」) 「ちょっとちょっと、ぶぅちんセンセ!」
指導医ぶぅちん(以下「ぶぅちん」) 「何かね、しまむら君」
しまむら 「いきなり内容がアサッテの方向に向かっていますよ。基礎免疫の話なんかしちゃって。明日からの感染症臨床にどう役立てればいいんですか? 忙しい感染症科の先生方はもう読んでないよ、きっと」
ぶぅちん 「まぁ待て、焦るな。すぐに使えるようになる知識はすぐに使えなくなるんだ。不明熱診療も日々の勉強も、焦りは禁物であるぞ」
しまむら 「ダイエットもですね、センセ!」
ぶぅちん 「……そうだね」
しまむら 「でも、もう少し噛み砕いて説明してください。そもそも略語や漢字が多くて読みにくいし、英単語も入り混じっているし」
ぶぅちん 「ヒトの体表には10の14乗個の常在菌がいて、そいつらと普段は仲良くつき合っているわけだ。しかし、感染が起きると、ある特定の菌やらウイルスやらがぶゎーっと増えてヒトの体内で何やら悪さをしよる。そこで、その『特定の菌やらウイルスやらの病原体』を同定して、免疫による防御システムを作動させる必要があるわけだ」
しまむら 「センセ、その10の14乗個ってどうやって数えたんですか?」
ぶぅちん 「先生が1個1個丹念に数えた」
しまむら 「……」
ぶぅちん 「過去には、T細胞受容体やB細胞の産生する抗体がものすごーく多様なので、『特定の病原体』が何であっても充分に対応できると考えられていた。ところが、そういったT細胞やB細胞が病原体に反応して活性化し、抗体なんかを産生するために、そもそも他の細胞(抗原提示細胞)からの刺激が必要だと分かってきたのが1980年代後半」
しまむら 「ふんふん」
ぶぅちん 「それで、そもそも『特定の病原体へのファーストコンタクト』、つまり『こいつは敵だ!準備しろ!』ということを免疫システムはどのようにやっているのかというのが、ここ20年ほどで長足の進歩を遂げた自然免疫なんです。innate immunityね」
しまむら 「ほぅほぅ」
ぶぅちん 「そこで大きく分けて2つの考え方が出てきた。一つはJaneway先生らによる『進化の過程で保存された、病原体の構造というかパターン(PAMPs)を認識するPRRが抗原提示細胞に発現していて、そこからシグナルが入るとT細胞やB細胞の活性化に結びついていく』という説。こちらが今のところ主流。もう一つはMatzinger先生らによる『細胞が病原体によってヤバい死に方をすると、そこからマジヤバイ警報(danger signal)が出て、それがT細胞やB細胞の活性化に結びついていく』という説。PAMPsに対応してdamage-associated molecular patterns(DAMPs)のような、細胞成分の一部でありながら免疫を活性化する構造があるのではないかと推定されていて、実際いくつか候補は見つかっているけど、これこそがDAMPsだ!というものは同定されていないのが現状」
しまむら 「なるほど。DAMPsとかPAMPsって見たら、なぜかISSAって単語を思い出したけど、ISSAって何かの略語でしたっけ、センセ?」
ぶぅちん 「……この2つの説で説明できること・できないことがそれぞれあるんだけど、最近ではこの2つの考え方自体が統合されつつある。ここでは深入りしない。Janeway先生は免疫学における『知の巨人』の一人で、彼の1989年の記念碑的論文では、驚くべき正確さで『自然免疫の研究で発見されるであろうこと』が予言されている[1]。Matzinger先生も面白い人で、初期の論文では自分の飼い犬を共著者にしたりしている[2]。インパクトファクター7の犬。ちなみにアフガンハウンド」
しまむら 「なんか知らんけど敗北感……」
ぶぅちん 「そして、そういったDAMPs(マジヤバイ警報)とかPAMPsとかを受け取ったマクロファージとか樹状細胞とかは、細胞内でinflammasomeというタンパク複合体を形成して、これが『風が吹けば桶屋が儲かる』ようなメカニズムで強力な炎症性サイトカイン IL-1βを活性化するわけです」
しまむら 「だいたい1学年に1人ぐらい、大食いで『マクロファージ』ってアダ名の医学生いるよね……。センセ、そういえば、末梢血の分画にマクロファージがありません!」
ぶぅちん 「先生の学年には『選り好みしない』って意味で『メ△ペ◯』ってアダ名のやつが……。そんなことはどうでもよろしい。しまむら君、免疫学の授業に出てなかったでしょ?」
しまむら 「免疫学の授業にも出ていませんでした!」
ぶぅちん 「……血管の中にいる間は『単球』、これが活性化して、炎症のある場所などで血管外に出ると『マクロファージ』、そこが結合組織内だと『組織球』です」
しまむら 「めもめも」
ぶぅちん 「IL-1βは、発熱の原因になるし、炎症局所に白血球を呼び寄せる働きもあるのです。で、ここ10年ちょっと『サイトカイン阻害療法』とか『生物学的製剤』っていうのが脚光を浴びていてね、『IL-1βを抑えるとどうなるの?』ということでIL-1βに対する生物学的製剤Anakinraというのが開発された。関節リウマチには残念ながら今一つ効かなかったし、毎日皮下注射ってことも他の生物学的製剤より不便だったので、関節リウマチには使われなくなった」
しまむら 「あら」
ぶぅちん 「しかし! これまでおしゃべりしてきたような自然免疫システムの理解によって、『もしかしたらAnakinraはinflammasomeの関連した病気には効くんじゃない?』ということで、徐々にそういう疾患に使われるようになってきた。まずはありふれた病気でありながら、時として治療が悩ましい『痛風発作』に使われた。尿酸の結晶がinflammasomeを活性化して足の親指のつけ根の関節にどかーんと関節炎を起こすのが痛風発作で、尿酸はDAMPsの一員なのではないかと言われているけど、これがAnakinra皮下注射(1回100mg、3日間連続)ですーっと治まる」
しまむら 「へぇぇ」
ぶぅちん 「Anakinraみたいに毎日皮下注射しなくてもいいCanakinumabやRilonaceptといった新規抗IL-1β製剤も出てきているみたいだね。10年以上前は『サイトカインは同じ作用を持ったものが複数あるから、1つだけサイトカインを抑えても他のサイトカインがその働きをカバーするから、炎症はよくならないんじゃないかな?』と言われていたけど、ベッドサイドでの効果は雄弁です。というか、免疫学の進歩を知らずに薬を使うことはほとんど不可能になってしまった」
しまむら 「センセ、ちょっと臨床っぽい話が出てきて安心しました! でも、感染症の臨床とどう結びついていくんですか?」
ぶぅちん 「例えば、原因不明の『発熱を繰り返す』患者さんがいるとして、しまむら君ならどうする?」
しまむら 「感染症か、リウマチ専門の先生に相談します!」
ぶぅちん 「リウマチ科医は『うちの県ではクッシーとかヒバゴン並に珍しい存在』って、某マイクロブログで言われていたぞ」(注:実話[3])
しまむら 「うーん……」
ぶぅちん 「原因がよく分からない発熱の患者さんは、総合内科、総合診療科、あるいは感染症科で診療されていることが多いと思うんです。いわゆる『不明熱』に限ると、検査の進歩に伴って、developed countryでは感染症や腫瘍が不明熱の原因になる比率は徐々に下がってきていて、一方でリウマチ性疾患の比率が上がってきています。さらに、不明熱が『診断不明』になる比率も上がっていて、これは別に『なぞの発熱』が増えたわけじゃなくて、もともと一定の比率で診断が難しい発熱の患者さんはいらっしゃって、感染症や腫瘍が『不明熱』の分類基準を満たす前にさくっと診断されるようになってきたからだと想像されます。そうした『最終診断が不明の不明熱』の予後は全般的に良好で、多くが6か月ほどすれば解熱すると言われているけど、そんな中でも関節の痛みや腹痛などで困っている患者さんがいらっしゃって、その中に『自己炎症症候群』の方が混じっているかもしれないと」
しまむら 「なるほど」
ぶぅちん 「そういうわけで、臨床免疫学の進歩を紹介しつつ、新しい『自己炎症症候群』という概念を紹介できればと思います」
しまむら 「締め切りを大幅に破っ……(ガシッ)」
ぶぅちん 「……ということで、後半の各論もおつき合いください」
しまむら 「ください」
【References】
1)Janeway CA Jr.: Approaching the asymptote? Evolution and revolution in immunology. Cold Spring Harb Symp Quant Biol. 1989; 54 Pt1: 1-13.
2)Wikipedia: Polly Matzinger.
http://en.wikipedia.org/wiki/Polly_Matzinger
3)medtoolzの日記
http://d.hatena.ne.jp/medtoolz/20091022
(続く)