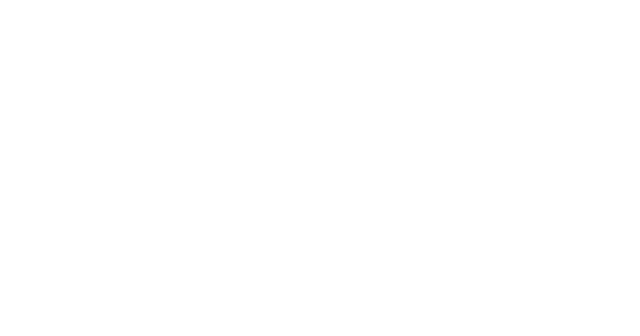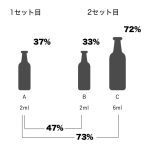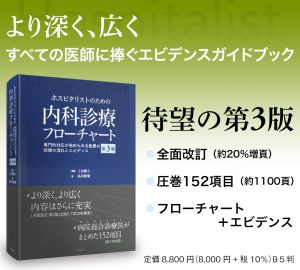小児肺炎の臨床研究の難しさ――あなたの肺炎とわたしの肺炎は違う?
はじめに
肺炎を診断したことがない、もしくはその患者の診療に携わったことがない医療者は、ほとんどいないだろう。日本では、年間およそ8~10万人が肺炎で死亡していると推計され、常に死因の上位に位置(死因の第4~5位で推移)している[1]。特に、高齢者医療に携わる方々にとって、肺炎は時に死因になる感染症として、一度はガイドラインに目を通し、自分の診療スタイルさえも確立し、その気になれば30分でも1時間でも語れるような、いわば内科の登竜門的な疾患なのではないだろうか。
では、小児における肺炎はどうだろうか? まず、お伝えしたいことは「小児科医も肺炎はよく診ている」ということである。発展途上国において、肺炎は5歳未満の死因の14%を占めている[2]。ただし、先進国においては、集中治療を要する症例はみられるものの致死的な症例は限られており、一般的なイメージとしては、経口摂取不良や軽度の酸素化低下に対して数日間の入院管理を要する軽症~中等症の疾患なのかもしれない。
英国、ノルウェーにおける健常な5歳未満における肺炎の年間発生率は32.8~33.8人/人口1万人で、その6~7割が入院を要している[3]。基礎疾患のある5歳未満を含む集団でみると、年間発生率は65.8人/人口1万人にも上るが、先進国における肺炎の致死率は1%以下である[3-5]。ちなみに、日本における5歳未満の肺炎での年間入院率は177~197人/人口1万人であり、これは他国の3~10倍以上の数値である[6]。でも、安心してほしい。ポーランドも同じぐらいの数値であることが報告されている[6]。すなわち、疫学研究の方法や対象患者の選定方法、肺炎の定義によって、変動しうる値であることを理解する必要がある。
そして臨床研究へ
話は変わるが、日本小児感染症学会認定指導医の受験申込時に提出する書類の一つに「感染症に関する筆頭原著の査読制度のある原著論文の提出(1編以上)」が挙げられている。そのため、教育研修プログラム施設では、フェローシップ期間中に原著論文の形になるような題材を探すことになる。当院は200床の全国的には中規模な小児専門医療施設であるが、これくらいの規模で、3~5年間ぐらいの後方視的研究で、簡単な統計解析が可能なぐらいの症例数を稼ぐことができる感染症となると、やはりcommon diseaseでの検討にならざるを得ない。となると、おのずと「肺炎」に目が向いていってしまうことは、想像にかたくないのではないだろうか。
さらに、培養検査やmultiplex PCR検査によって微生物学的な検討が可能である点も、この動向に追い打ちをかけている。特に近年は、multiplex PCR検査の普及によって、呼吸器ウイルスの検出が手軽に短時間(約1時間)でできる時代になった。これまで“some viral infection”としてあきらめていた病原体診断ができるようになったとき、小児科医は手を震わせたのである。
肺炎は、抗菌薬適正使用の主要な対象疾患として考えるべき点も多い。レセプト情報・特定健診等情報データベースから得られた国内疫学データによると、急性下気道感染症と診断された16歳未満の患者数は、4年間(2013~2016年)累計で1800万人ほど。そのうちの36.9%に内服抗菌薬が処方され、その内訳はマクロライド系(47%)が最多で、次いでセフェム系(37%)が多く、その9割は第3世代セフェムであった[7]。
また、小児市中肺炎の「近代疫学の祖」とも言えるEPIC Study(米国)では、入院を要した小児市中肺炎2358例のうち66%がウイルス性肺炎で、細菌性肺炎は15%であったが、88%の症例に対して抗菌薬が投与されており、その多くは不必要であった可能性が示唆されている[8]。同じく、比較的最近のデータとして、小児市中肺炎に対してウイルス性か細菌性かを区別するためのスコアリングシステムを検討したVALS-DANCE Study(スペイン)では、495例のうち52.7%がウイルス性、47.3%が細菌性と診断されているが、実に94%の症例に対して抗菌薬が投与されていた[9]。
このように、小児の下気道感染症(肺炎を含む)にフォーカスを当てて考えてみると、幸いにも国内における臨床データも少なく、この枠組みで臨床研究を考えてみることに異論はないだろう。この先に待ち構えていた苦難の日々を共有させていただくとともに、どのようにしたらこのcommon diseaseの国内での知見を積み重ねていくことができるのかを、ぜひ一緒に考えていただきたい。
こうしてあの臨床研究は「星」になった
まず、臨床的にウイルス性肺炎か細菌性肺炎かを区別することは難しい。特に小児では、自律的な喀痰の排泄が困難であるため、下気道からの培養検体が得られず、多くの場合は起因微生物が不明である。EPIC Study[8]では、鼻腔ぬぐい液のmultiplex PCR検査で検出されたウイルスを、肺炎の起因微生物と想定している。細菌性肺炎と診断された症例の多くは血液培養や胸水培養で細菌が検出された症例であり、下気道検体の培養検査は1%弱しか実施されていない。
ここで1つのClinical Questionがある。臨床医は肺炎で入院してきた患者に対して、抗菌薬を開始する/しないをどのように判断しているのだろうか? 大半の小児科医は「重症度で判断する」と答えるのだろうが、その重症度を規定する因子もそれぞれである。「子どもは脆弱である」という暗黙の前提があり、多くケアをすることが、より良いことであると信じられている風潮すらある[10]。そこで、入院を要した肺炎の症例に対して、臨床医が抗菌薬を開始する因子を解析・検討してもらうことにした(この研究は、当センター倫理審査委員会で承認を受けた〔承認番号ACHMC-2021043〕)。
2017年1月~2018年12月に入院した症例のうち、「肺炎」「気管支炎」「細気管支炎」「気管支喘息」の保険病名が付いている患者を母集団として、その患者の退院時サマリーに記載された病名を真の診断名として、下気道感染症の入院患者を選定した。実際、およそ400例の電子カルテを開き、研究の対象症例は291例であった。そのうち、肺炎と診断された症例は112例で、60例(53.6%)に抗菌薬が投与されていた。抗菌薬投与群と非投与群の因子を比較したところ、多変量解析で統計学的有意差を認めたのは、中耳炎あり(P=0.01)とCRP上昇(P<0.001)の2因子であった。その一方で、基礎疾患の有無や、呼吸数、発熱や気道症状の持続期間、人工呼吸器/高流量鼻カニュラ酸素療法/ICU入室の有無は、抗菌薬投与を規定する因子ではなかった。
このデータは、単に、国内の単施設における抗菌薬の処方傾向の話なので、これをもって何かを提言できるものではないことは重々に理解している。しかし、臨床経過や重症度によって抗菌薬投与の判断がなされているわけでないことは驚きで、むしろ「やっぱりお前(CRP)か……」と思わされるデータでもあった。海外では入院症例の9割弱で抗菌薬が投与されている状況もあり、肺炎に対する抗菌薬適正使用の観点から参考になるデータになる可能性も考え、論文化に向けて歩みを進めてみることにした。
結論から言うと、いくつかの国内機関誌にトライしてみたが、その論文が日の目を見ることはなかった。rejectの主な理由としては、単なる単施設における処方傾向であることはもちろんだが、肺炎の診断基準に対する意見が多かった。本研究では、DPC病名および電子カルテの記載をもって、臨床的に肺炎と診断された症例をinclusionしていたため、X線検査や培養検査の結果は診断基準に含めていない。それでは、臨床研究にふさわしい「肺炎の診断基準」とはいったい何だろうか?
臨床研究にふさわしい肺炎の診断基準とは?
肺炎とは「肺実質における急性感染症の徴候と症状」である[3,11]。より臨床的に「身体所見や胸部X線検査などで肺実質病変を認める根拠があり、典型的には発熱・呼吸器症状を伴う」[12]や「発熱、鼻汁、咽頭痛、咳嗽などの急性呼吸器感染症症状を伴い、胸部X線像やCTなどの画像検査において肺に急性に新たな浸潤影が認められるもの」[13]と定義しているものもある。
しかし、先進諸国において肺炎の明確な診断基準は存在しない。実際に、細菌性肺炎の診断方法についてのsystematic reviewでは、25文献で11種類の異なる診断基準が採用されていた[14]。胸部X線検査は肺炎の決定的な診断基準と思いきや、X線検査を診断基準に含めた研究は上記25文献のうち5文献だけである[14]。X線検査は撮影条件で所見すら変わるものであり、その画像を見る人によって判断も異なる。小児科医が肺炎と診断した画像の17.2%は小児放射線科医が読影すると正常と判断され[15]、2人以上の専門家が画像評価した場合は22%で評価の乖離が見られた[16]。日常のカンファレンスの一幕を思い起こしても、「これは肺炎」とか「これは軽めの肺炎」とか「これは細気管支炎」とか、人によって思っていることは違い、結果的には上級医の意見が採用されていることだろう。ちなみに、医療的なリソースが限られている国では肺炎の致死率は依然として高く、WHOはそのような国でも肺炎が診断できるように、唯一といってよい肺炎の診断基準を制定している[17]。それによると、咳嗽や呼吸困難がある5歳未満の小児で、呼吸が速い患者(2か月未満;≧60回/分、2~11か月;≧50回/分、1~5歳;≧40回/分)を「肺炎」と定義し、その症例に対して抗菌薬投与が推奨されている。
では、小児肺炎に関する大規模臨床研究では、どのようなinclusion criteriaが用いられているのか? 代表的な研究と最近実施されたRCTのinclusion criteriaをいくつか抜粋し、まとめてみた(表)。どの診断基準であれば、皆さんは納得がいくだろうか? これを見ると、先進国における前向き研究では、CAP-IT trialを除き、ほとんどの研究でX線検査所見をinclusion criteriaに含めている。特にEPIC Studyでは、2名以上の小児放射線科医が読影しており、肺炎として納得のいくものであると個人的には思ってしまう。HOPE Studyは、初診時は訓練された臨床医がX線検査を読影しているが、フォローアップで撮像されたX線検査は呼吸器科医もしくは放射線科医の2名以上が読影していた。The SAFER Randomized Clinical Trialに関しては、X線検査の読影基準は文中に記載されていなかった。一方で、パキスタンで実施された研究はWHOの肺炎診断基準のvalidation studyの類いであり、X線検査所見は含まれていなかった。
表 代表的な小児肺炎の臨床研究で用いられているinclusion criteria
| 研究/PMID | 掲載雑誌/ 年 | 肺炎のinclusion criteria |
| EPIC Study/ 25714161 | NEJM /2015年 | 米国、多施設前向きコホート研究 18歳未満の肺炎入院患者急性感染症:発熱・悪寒,または発熱・低体温,または白血球血症・低白血球血症急性呼吸器疾患:新規咳嗽,喀痰,胸痛,呼吸困難,多呼吸,聴診異常,呼吸不全肺炎に合致する所見:入院前後72時間以内の胸部単純X線検査で硬化像,浸潤影ないし胸水あり(小児放射線専門医が読影) |
| RETAPP Clinical Trial/ 32609980 | NEJM /2020年 | パキスタン、多施設、double-blind, randomized, noninferiority trial 生後2~59か月の小児、外来患者咳嗽や呼吸困難がある呼吸数の増加(2か月未満;≧60回/分、2~11か月;≧50回/分、1~5歳;≧40回/分) |
| The SAFER Randomized Clinical Trial/ 33683325 | JAMA Pediatrics /2021年 | カナダ、2施設、double-blind, randomized, noninferiority trial 生後6か月から10歳以下、外来患者受診前48時間以内に発熱(腋窩温≧37.5℃、口腔温≧37.7℃、直腸温≧38℃)頻呼吸(1歳未満;≧60回/分、1~2歳;≧50回/分、2~4歳;≧40回/分、4歳以上;≧30回/分)、努力呼吸(頭蓋筋の使用、胸骨上窩の陥没、肋間の伸展)、肺炎に矛盾しない聴診所見胸部X線検査で肺炎と一致する所見救急外来担当医によって肺炎と診断される |
| CAP-IT trial/ 31123008 The CAP-IT Randomized Clinical Trial/ 34726708 | BMJ Open /2019年 JAMA /2021年 | 英国・アイルランド、他施設、double-blind, placebo controlled RCT 生後6か月以上、体重6~24kg、外来および入院患者臨床的に肺炎と診断され、退院時にアモキシシリンによる治療を予定登録時にβラクタム系抗菌薬による治療をまったく受けていないか、48時間以内に開始された治療であること 肺炎の臨床診断は、以下のすべてに該当するものと定義 咳嗽(受診前96時間以内に出現したもの)38℃以上の発熱、または受診前48時間以内の発熱呼吸困難または局所的な胸部所見(以下のうち1つ以上;鼻翼呼吸、陥没呼吸、腹式呼吸、打診での局所的な濁音、局所的な呼吸音減弱、非対称性のcrackle) |
| HOPE Study /31023759 | BMJ Open /2019年 | オーストラリア・ニュージーランド・マレーシア、多施設、double-blind, placebo controlled RCT 生後3か月から6歳未満の入院患者決められた居住地域に住んでいる、民族的制限のない小児入院時に重症肺炎の特徴(37.5℃以上、陥没呼吸を伴う頻呼吸〔生後12か月未満;≧50回/分、生後12か月以上;≧40回/分、SpO2<92%〕、胸部X線検査で浸潤影あり〔訓練された臨床医が読影〕)静注抗菌薬開始から3日以内に解熱、呼吸症状改善、SpO2≧92%、アモキシシリン・クラブラン酸へ内服変更が検討されている入院時の症状持続期間が7日以内であること |
表で示したような診断基準を、後方視的研究で再現することは、果たして可能だろうか? 発熱や呼吸器症状などに関しては十分に適応可能である。しかし、X線検査所見を2名以上の臨床医で読影することすらハードルが高く、さらに専門家に読影してもらえる施設は非常に限られているのではないだろうか。個人的には、現状の体制では、誰しもが納得するような診断基準を用いて小児肺炎の後方視的研究を運営していくことはやはり困難で、たとえ論文化したとしても、そのときのreviewerがどのように判断するかに依存した、非常に脆いものになってしまう気がした。
今後の課題(と、あの論文の行く末)
繰り返しになるが、小児肺炎はcommon diseaseであり、最初に簡単な統計解析を伴う後方視的研究を行う題材として優れている側面がある。しかし、明確な診断基準がなく、誰しもが納得するinclusion criteriaを設定することが難しいものであった。あなたの思っている肺炎と、私が思っている肺炎は、似て非なるものなのだ。また、国内の医療機関にも、放射線科医へのアクセスが優れた病院もあれば、そうでないところもある。誰しもがアクセス可能な、AI技術を用いたX線解析ソフトがあり、「AI判定で90点以上であれば浸潤影あり」などの基準ができるとよいのだが……。さらに、小児に限った話ではないが、国際的な肺炎の診断基準の確立も待たれるところである。
ちなみに、あの研究は、400例のカルテをこじ開けた苦労を何とか昇華させるために、いろいろと視点を変えて解析し(統計の先生が見たら怒られてしまうが)、最終的には「気管支炎で入院した患者に対して鼓膜観察を実施しない因子」の解析に至ったのだが、結果的は完全に日の目を見る機会を失い、PCの奥底に眠るだけのデータになってしまった。人は400例の電子カルテを開くと、その病院での、その疾患に関して一通り極めた気持ちにさえなる。しかし、rejectに次ぐrejectで、その話をすると次第に目の輝きが失われ、笑顔がなくなり、最後は目線すら合わなくなってしまった。IDATENのKANSEN Journalという、1万3000人超の目に触れる場所にデータを提示することで、彼の苦労と心労に対する、せめてもの弔いとしたい。
【References】
1)厚生労働省: 令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数) 結果の概要.
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai20/dl/kekka.pdf
2)WHO: Pneumonia, 2021.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
3)Harris M, Clark J, Coote N, et al: British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax. 2011 Oct; 66 Suppl 2: ii1-23.
4)McAllister DA, Liu L, Shi T, et al: Global, regional, and national estimates of pneumonia morbidity and mortality in children younger than 5 years between 2000 and 2015: a systematic analysis. Lancet Glob Health. 2019 Jan; 7(1): e47-e57.
5)Jain S, Williams DJ, Arnold SR, et al; CDC EPIC Study Team: Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. children. N Engl J Med. 2015 Feb 26; 372(9): 835-45.
6)Madhi SA, De Wals P, Grijalva CG, et al: The burden of childhood pneumonia in the developed world: a review of the literature. Pediatr Infect Dis J. 2013 Mar; 32(3): e119-27.
7)Uda K, Okubo Y, Kinoshita N, et al: Nationwide survey of indications for oral antimicrobial prescription for pediatric patients from 2013 to 2016 in Japan. J Infect Chemother. 2019 Oct; 25(10): 758-763.
8)Jain S, Williams DJ, Arnold SR, et al; CDC EPIC Study Team: Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. children. N Engl J Med. 2015 Feb 26; 372(9): 835-45.
9)Tagarro A, Moraleda C, Domínguez-Rodríguez S, et al; VALS-DANCE Study Group: A Tool to Distinguish Viral From Bacterial Pneumonia. Pediatr Infect Dis J. 2022 Jan 1; 41(1): 31-36.
10)Coon ER, Young PC, Quinonez RA, et al: Update on Pediatric Overuse. Pediatrics. 2017 Feb; 139(2): e20162797.
11)Bradley JS, Byington CL, Shah SS, et al; Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America: The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2011 Oct; 53(7): e25-76.
12)Barson WJ: Pneumonia in children: Epidemiology, pathogenesis, and etiology. UpToDate. Mar 14, 2022.
https://www.uptodate.com/contents/pneumonia-in-children-epidemiology-pathogenesis-and-etiology
13)尾内一信, 岡田賢司, 黒崎知道(監), 小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会(作成): 小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017, 協和企画, 2016, p.202.
14)Lynch T, Bialy L, Kellner JD, et al: A systematic review on the diagnosis of pediatric bacterial pneumonia: when gold is bronze. PLoS One. 2010 Aug 6; 5(8): e11989.
15)Nascimento-Carvalho CM, Araújo-Neto CA, Ruuskanen O: Association between bacterial infection and radiologically confirmed pneumonia among children. Pediatr Infect Dis J. 2015 May; 34(5): 490-3.
16)Elemraid MA, Muller M, Spencer DA, et al; North East of England Paediatric Respiratory Infection Study Group: Accuracy of the interpretation of chest radiographs for the diagnosis of paediatric pneumonia. PLoS One. 2014 Aug 22; 9(8): e106051.
17)WHO: Revised WHO classification and treatment of childhood pneumonia at health facilities― EVIDENCE SUMMARIES.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/137319/9789241507813_eng.pdf