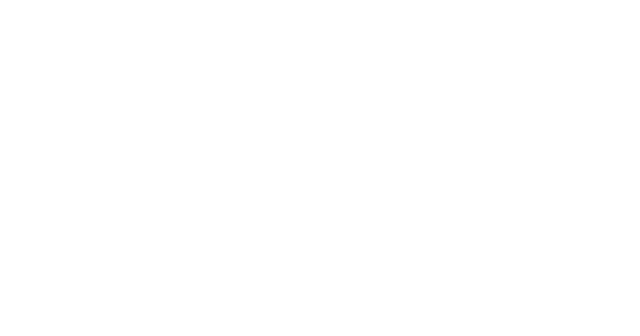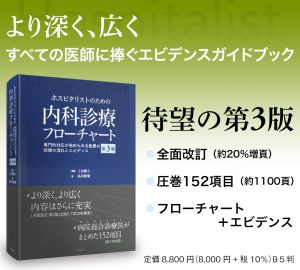成人でみられる先天性免疫異常―Common variable immunodeficiency―について(3/3)
合併症
合併症は大きく3つに分類される。1)急性もしくは慢性の感染症、2)炎症性もしくは自己免疫性、3)悪性腫瘍である。CVIDを理解するにあたって重要なことは、感染症とその結果である構造的な破壊と、もともと存在する免疫異常からくるものを分類することである。表5に挙げた合併症を検索することが必要だろう。
| ・特異的な疾患に対する個別の検査:真菌・抗酸菌抗原 (肉芽腫性病変がある場合) ・便中の脂肪(吸収不良がある場合) ・基礎値としての呼吸機能検査、胸部CT |
1.感染に関連した合併症
特に多い感染症は細胞外寄生をする微生物、例えばインフルエンザ桿菌や肺炎球菌による呼吸器感染症で、上気道炎の再発を繰り返すことによる慢性副鼻腔炎や、重症の、もしくは再発する肺炎により気管支拡張症が生じる。
いくつかの研究[6]によると、重症感染症が肺構造の破壊を惹起するが、この結果はIgG抗体レベルのみが決定要因ではないということを意味している。合併症が感染症のみの場合で予後が改善された[6]のは、免疫グロブリンの導入による恩恵であろう。
そのほかに知られているものとして、腸管感染症ではジアルジアに罹患しやすい。また、Ureaplasma urealyticumによる反復性の尿路感染性、マイコプラズマ感染症による関節炎、エンテロウイルスによる髄膜脳炎や皮膚筋炎が報告されている。これらはCVIDに限られるものではなく、ほとんどは抗体欠乏のある患者に限られる。
2.自己免疫疾患に関連した合併症
CVIDには、多様な遺伝的背景に関連する自己免疫疾患、免疫増殖性の病態に起因する合併症がある。これらの病態が早く発症した場合に合併症の頻度が高くなるというエビデンスがあり[9]、このタイプのCVIDは早い段階での死亡のリスクがあると考えられている。特に血球減少は約10%にもみられ、免疫性血小板減少、溶血性貧血、脾腫の頻度が高く、一般的な発症率より高い。クラススイッチしたメモリーB細胞のアイソトープが末梢血中で減少することなどが機序として考えられている。
そのほかの自己免疫疾患としては、悪性貧血、甲状腺疾患、白斑症などがCVIDの患者の5%以上でみられるが、これらも一般にみられる頻度より高い。また、頻度は少ないが肉芽腫が不明熱の原因となることがある[10]。リンパ浸潤性疾患としては、リンパ間質性肺炎や原因不明の腸症がある。これらの疾患にはリンパ節腫脹や肝脾腫(特に腸症)が合併することが多い。
3.悪性腫瘍に関連した合併症
CVID患者の2~8%で、診断された時点で非ホジキンリンパ腫の合併がみられる。その多くはB細胞タイプ、分化型で、またEBV陰性であるといわれている[11]。
これらの臨床的な分類により予後はある程度予測でき、合併症が感染症のみの場合は予後良好でCVIDがない場合とほぼ変わらないが、リンパ系の悪性腫瘍を合併している場合は最も予後が悪く、診断から30年時点での生存率は約50%である[6]。
Mutationを引き起こす疾患
免疫表面マーカーにより、CVIDは単一の疾患ではなく症候群であることが分かっていたが、近年の遺伝子検査により、CVID様の臨床症状をきたす遺伝子異常が明らかになってきた(表6)。ICOS欠損やCD19遺伝子変異である。
対照的に、B細胞機能にわずかな影響を与える遺伝子の多型性もみられる(表6に示したTACIやBAFF-Rといったもの)。
CVIDの10%程度では免疫グロブリンのクラススイッチの欠損が認められ、DNA修正蛋白であるMsh5がCVIDや選択的IgA欠損に関連しているといわれている。これらの異常とCVIDの合併症である気管支拡張症や肉芽腫、自己免疫、リンパ系悪性腫瘍との関連性については、今後の研究で解明されることが期待される。
| 蛋白の欠損 | 遺伝子の部位 | 遺伝様式 |
|
ICOS |
2q33 |
常染色体劣性 |
|
CD19 |
16p11.2 |
常染色体劣性 |
|
TACI |
17p11.2 |
常染色体優性または劣性 |
|
BAFF-R |
22q13 |
常染色体劣性(おそらく) |
|
MSH5 |
6p22.1-p21.3 |
不明 |
マネージメント
マネージメントの目的は、生命を脅かすような細菌感染を予防するため、適切な量の免疫グロブリンを投与することである。通常はトラフレベルを0.4~0.6g/Kg/月として、それを複数回に分割して静脈投与もしくは皮下注射することで、ブレイクスルーの細菌感染症は著明に減少する。ただし、個々の患者によって感染を予防できる免疫グロブリン値は異なるため、単にIgGのトラフレベルが十分であるわけではないことに注意が必要である。
合併症の治療はリスクに応じて行なうが、重症の自己免疫疾患、肉芽腫疾患、リンパ浸潤性疾患においてはステロイド治療が施行される。このあたりの治療に対しては、免疫抑制剤や生物学的製剤などの使用も現在議論されているところである。
CVIDの場合は、他疾患との鑑別も含めて適切な専門家への紹介が必要になることが多いが、まずは疑うことが大前提である。疑わしい場合には初期的な検査を行ない、診断を進めていくことになる。
自己免疫性疾患や悪性腫瘍が疑われる場合は各専門家に相談し、それらの原因として純粋に原発性免疫不全症が疑われる場合には、原発性免疫不全症の専門家サイトである「PIDJ-Primary Immunodeficiency Database in Japan」を参考にするとよいだろう。
謝 辞
本稿の執筆にあたっては、国立成育医療研究センター感染症科の斉藤昭彦先生および同免疫科の河合利尚先生にお世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。
<References>
6.Chapel H, et al: Common variable immunodeficiency disorders: division into distinct clinical phenotypes. Blood. 2008 Jul 15; 112(2): 277-86.
9.Dalal I, et al: The outcome of patients with hypogammaglobulinemia in infancy and early childhood. J Pediatr. 1998 Jul; 133(1): 144-6.
10.Fernandez-Ruiz M, et al: Fever of unknown origin in a patient with common variable immunodeficiency associated with multisystemic granulomatous disease. Intern Med. 2007; 46(15): 1197-202.
11.Gompels MM, et al: Lymphoproliferative disease in antibody deficiency: a multi-centre study. Clin Exp Immunol. 2003 Nov; 134(2): 314-20.
(おわり)