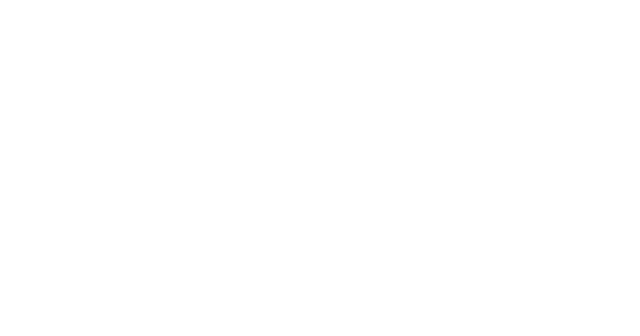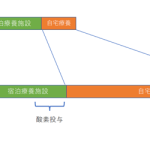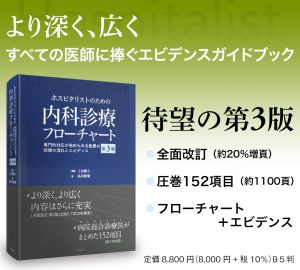ESBL産生菌検出のピットフォール
Extended-spectrum β-lactamase(以下、ESBL)はpenicillin、cephalosporin(cephamycinは除く)、aztreonamの分解能を有し、クラブラン酸などのβ-lactamase阻害剤の阻害を受けるという特徴を有するβ-lactamaseであり、その産生はグラム陰性桿菌の多剤耐性化の原因の一つとして知られています。ESBL産生菌であれば抗菌薬感受性検査の結果が「感性“S”」と判定されていたとしてもすべてのpenicillin、すべてのcephalosporin(cephamycinは除く)、aztreonamは臨床的には無効であると判断するのが適切と考えられているためその拾い上げは重要です。例えばin vitroの感受性試験で第4世代cephalosporinであるcefepimeに対する最小発育阻止濃度(以下、MIC)が“S”の範囲内であったとしてもその菌がESBL産生菌と判定されれば臨床医には「耐性“R”」として報告すべきとされています。また、多くの場合はESBLをコードする耐性遺伝子はプラスミド上に存在しており、それ故に菌種内、菌種間での耐性の拡散のpotentialがあるため、感染症治療のみならず感染制御の観点からも検出の必要性があります。
ではそのESBL産生菌の検出はどのように行なわれるのでしょうか?
米国の臨床検査標準委員会であるClinical and Laboratory Standards Institute(以下、CLSI)ではESBL産生の可能性のある菌の拾い上げであるInitial screen test(以下、スクリーニング)と実際にESBLを保有していることを確認するためのPhenotypic confirmatory test(以下、確認検査)の2段階での検出を推奨しています[1]。
スクリーニングではcefpodoxime, ceftazidime, cefotaxime, ceftriaxone, aztreonamの感受性がある境界値より低下していないかを微量液体希釈法あるいはディスク拡散法で検査します。ここで注意が必要なのは
① ここで用いる感受性の境界値は通常の抗菌薬感受性検査の“S”の境界値よりも厳しいこと(例えば腸内細菌のcefotaximeの“S”のrangeはMIC≦8μg/mlですが、ESBLスクリーニングではMIC≧2μg/mlを陽性とします)
② 必ず上記の薬剤のうちの複数の薬剤でスクリーニングすべきであること(ESBLは異なる酵素活性を有するいくつかの種類の酵素群<TEM型、SHV型、CTX-M型など>の集合名称でありそれぞれの酵素ごとに得意とする薬剤が異なるため、複数の薬剤をスクリーニングで用いなければESBLの産生を見逃してしまう恐れがある)
の2点です。①に関してはESBL産生菌の約40%は少なくとも一つの広域βラクタム薬にCLSIの基準で“S”を示し、20%はすべての広域βラクタム薬で“S”と判定されるという報告もあり[2]、このことを意識していなければ「見逃し」の危険があります。
スクリーニングが陽性となると次は確認検査に進みます。確認検査はESBLがβ-lactamase阻害剤であるクラブラン酸により阻害されることを利用して、微量液体希釈法やディスク拡散法でクラブラン酸の共存によりceftazidimeあるいはcefotaximeに対する感受性が回復することを検出することで行ないます。ここでも上記の理由によりceftazidime, cefotaxime両薬剤について検査を行なうことが求められます。ここで陽性となって最終的に「ESBL産生菌」という評価がなされます。
CLSIの検査法も万能ではありません。CLSIがESBL産生菌検出の対象としているE. coli, K. pneumoniae, K. oxytoca, P. mirabilisにおいても狭域のβ-lactamaseの過剰産生や外膜蛋白の発現低下による偽陽性、プラスミド性のAmpC β-lactamaseの同時保有による偽陰性などが起こりえます[2]。このような検査の「限界」による偽陰性が許されないような臨床状況(例えばこれらの菌による重症敗血症など)ではスクリーニング陽性の段階でESBL産生菌扱いとして治療を進めたほうが安全な場合もあるかもしれません。
Enterobacter spp. Citrobacter spp. Serratia spp.などの染色体性のAmpC β-lactamaseを有する腸内細菌ではAmpC β-lactamaseの過剰産生により第3世代セファロスポリンが分解されることでクラブラン酸によるESBL阻害効果がマスクされてしまい、確認検査が偽陰性となることが懸念される[3]ため、CLSIはこれらの菌種はESBL検出の対象としていません(ただし、これらの菌によるESBL保有は報告されています)。
また、ESBL産生菌の検出に固執せず、CLSIのMIC breakpointをより厳しく設定することでESBL産生菌も含めて一律に対応が可能ではないか、と考える専門家もおり、実際に米国以外の多くの国ではより厳しいMIC breakpointが設定されています[2]。CLSIのcefepimeのsusceptibleのbreakpointは臨床的な予後と相関していないのではないか、ということを示唆する報告[4]もあります。
抗菌薬選択に有用な抗菌薬感受性検査ですがCLSIのESBL産生菌の検出法一つをとってみてもこれだけの「注意点」や「限界」があり、これらを踏まえて初めて臨床で役立つ情報となります。正しく施行されていない検査結果は解釈が困難であり時に有害となる場合すらあります。例えば、ある病院で日常的に感受性判定を行っていない細菌(例えば嫌気性菌)の抗菌薬感受性検査を臨床医に依頼されて、検査室が困った挙句に他の菌の基準をその菌の感受性判定に根拠無く転用して感受性を報告する、などといったこともありえない話ではありません。検出菌がメチシリン耐性表皮ブドウ球菌なのにMICが低いからカルバペネムに「感性“S”」と報告されていた、などというのも聞いたことがあります。こうして得られた結果を根拠に抗菌薬が選択されるのは危険なことです。臨床医と検査技師が適切な検査法と報告法についての情報を共有して適正な検査が行われるような環境を維持するように努めたいところです。
さらに今後、新たな型の耐性菌の出現や拡散(CLSIも2008年の改訂で、米国で拡散を示している腸内細菌のKPC型 carbapenemaseについて新たに言及しています)、現在の問題点を克服するための新たな検査法の開発などで抗菌薬感受性検査がさらに複雑化していくことが予想されますが、これらを適切に解釈、検討して臨床医にとって理解しやすく、安心して使える形で現場に導入していくこと、さらには本邦の耐性菌の疫学的状況、医療事情に合わせた検査体系を確立していくことが今後、感染症科医、臨床検査医に求められる役割の一つではないかと考えます。
Take Home Message
- CLSIの定めるESBL産生菌の検出法はInitial screen testとPhenotypic confirmatory testの2段階でなされ、適切に施行するための具体的な方法が定められている。
- 適切な方法で検査を行なってもESBL産生菌検出の偽陽性、偽陰性は起こりうる。現在の方法の限界や問題点を認識し、臨床状況によっては柔軟な解釈をとることもありうる。
- 臨床医は自らの施設の細菌検査、感受性試験が適切な方法で行なわれ、適切に報告されているかどうか問題意識を持ち、疑問点があれば検査技師、感染症科医、臨床検査医などと話し合う。
- 感染症科医は微生物検査室と常時情報交換し現状を把握するとともに適切な検査、報告を行なうための知識を持ち臨床に有益な情報を提供できるように検査室を運営する、あるいは運営ができる検査技師、臨床検査医などと連携する。
<References>
- Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility tasting; 18th informational supplement. M100-S18. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, 2008.
- Paterson DL, Bonomo RA. Extended-spectrum β-lactamase: a clinical update. Clin Microbiol Rev 2005; 18:657-686
- Pitout JD, Laupland KB. Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae: an emerging public-health concern. Lancet Infect Dis. 2008; 8:159-166
- Bhat SV, Peleg AY, Lodise TP Jr, Shutt KA, Capitano B, Potoski BA, Paterson DL.. Failure of current cefepime breakpoints to predict clinical outcomes of bacteremia caused by gram-negative organisms. Antimicrob Agents Chemother. 2007; 51:4390-4395